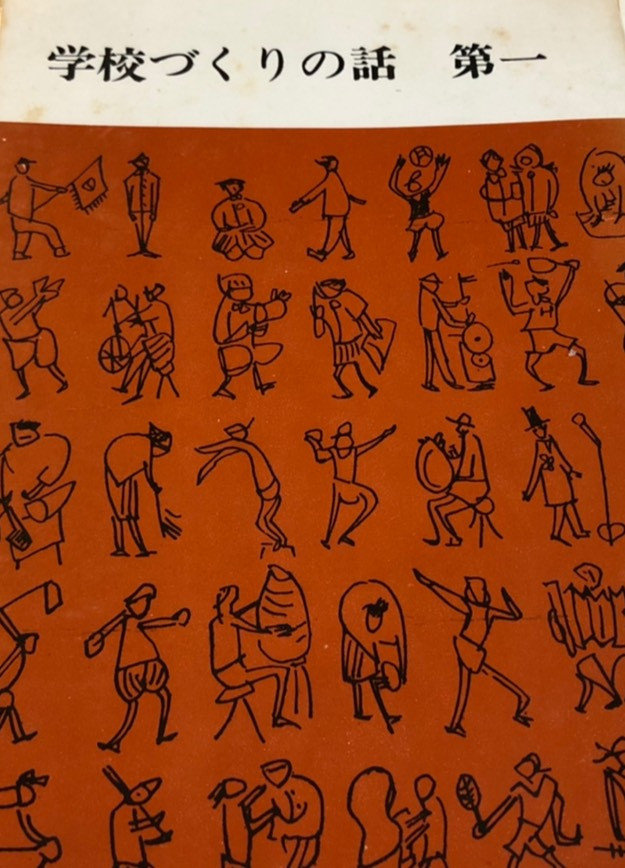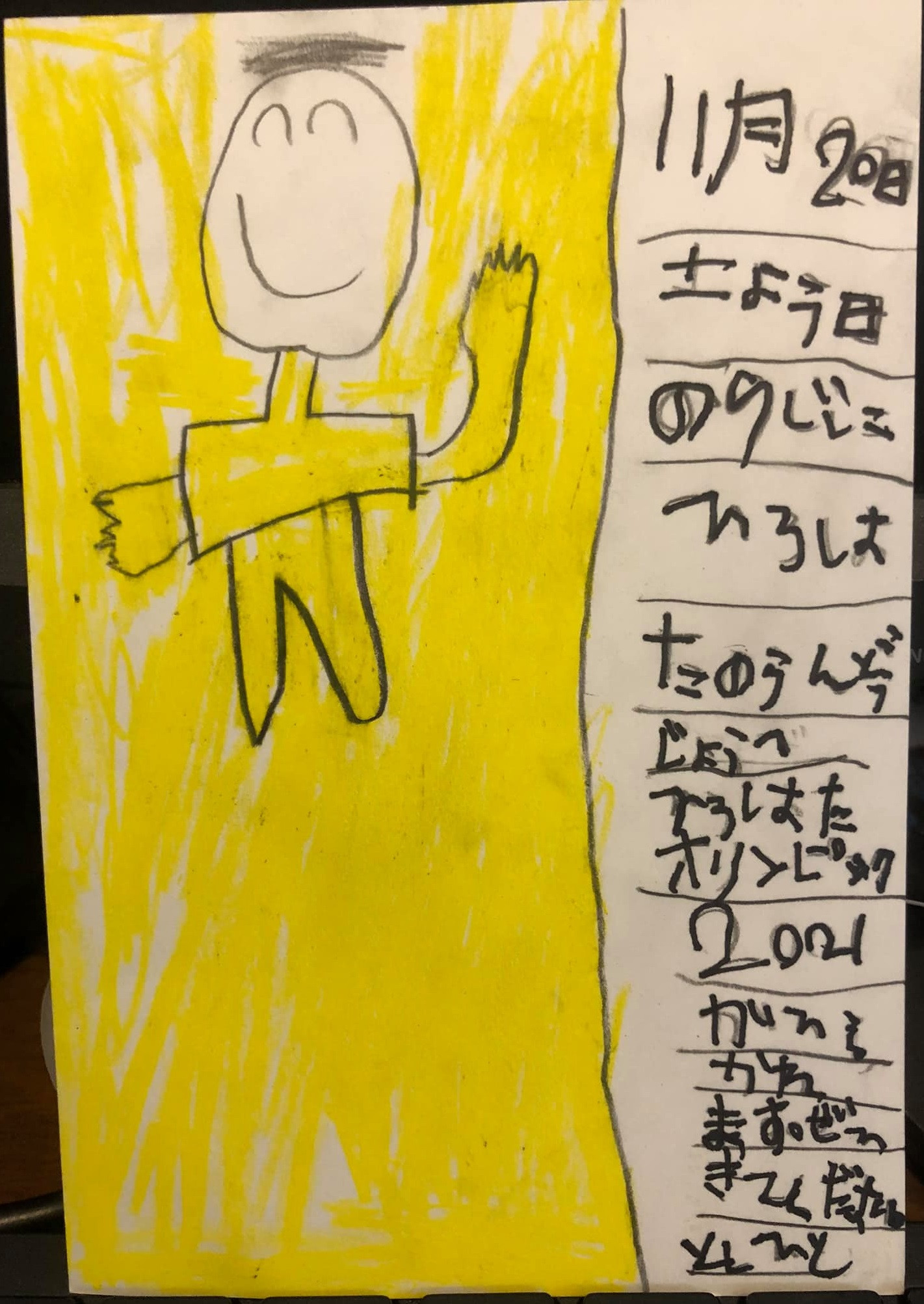1972年だったと思います。日時が確かでないのは、私の当時の日記が行方不明になったことと、岡崎市教育委員会に問い合わせても「鈴村正弘教育長欧州訪問」の詳しいデータが何も残っていないためです。
当時英国ロンドンで生活していた私のもとに母千代子から〝伝令〟が飛んできました。
「教育長になられた鈴村先生が近くヨーロッパを訪問なさいます。英国ではあなたがお世話をすると言っておきましたからよろしく。私たちの関係は絶たれていても、これは別問題。あなたが鈴村先生から受けた御恩は忘れないでそちらで返すように」
千代子とはその数年前に対立が激化、親子関係を絶ちその後一切連絡を取っていませんでした。居場所についても知らせてありませんでしたが、母は私の友人から連絡先を聞きだして連絡してきたのです。
鈴村にお世話になったと言われても、私にその記憶はありません。覚えているのは、中学高校時代に何度か城北中学の校長室に呼び出されてお説教を受けたことです。それを御恩と言い切る千代子に「相変わらずだな」と思いましたが、「教育長になった鈴村さんと会って日英教育談義をやるのも悪くないな」という好奇心がないわけではなく、受け入れることにしました。
 |
| 鈴村正弘と“おかん”(1965年) |
滞在していたホテルに行くと、鈴村は相変わらずの人懐っこい笑顔で温かく迎えてくれました。その手に左翼的論調で鳴る月刊誌『世界』を持っているのが気になりましたが、私からあえて触れなかったためか、話題になることはありませんでした(後になって分かったことのひとつですが、鈴村の知識欲には思想の境界はなく、俗に言う右から左まで幅広い層の人や書物から吸収していました。また人的交流もあったようです)。
鈴村は私たち親子の関係修復を試みたかったようですが、私にその気がないと分かるとそこにこだわることなく、英国の教育事情を熱く語る私の話に耳を傾けてくれました。そして、翌日連れて行った現地校でも校長や教員の話を熱心に聴き、いくつも質問をしていました。その姿に、英国の教育環境の良いところがふるさと岡崎に少しでも生かされるのではないかと望みを持ちましたが、残念ながらその後ロンドンや東京に伝わってくる「三河管理教育」の現状にはその辺りの〝効果〟は認められませんでした。
私がお世話をしたと言ってもその程度で、鈴村は翌日、次の訪問地に向けて慌ただしく旅立っていきました。
しばらくして兄から結婚したとの報告が入りました。鈴村夫妻に仲人をお願いしたと聞き、千代子に押し切られる彼の姿を思い浮かべて「かわいそうに。でも、おふくろの言いなりになるのも兄貴らしいな」と思いました。
鈴村は多忙を極めた時期なのにわざわざ長野にある結婚相手の実家にまで出かけて結納に同席したとのこと。彼の面倒見の良さには舌を巻きました。
後に列席者から聞いたところによると、結婚披露宴では「ロンドンに留学している弟さんから祝福の国際電話が入りました」と司会者が紹介し、会場が盛り上がったそうです。結婚することさえ知らされていなかった私が電話を入れるはずがありません。また、義澄がそんな演出を思いつくこともありえません。その話を聞いた時には、義澄はすでに他界していましたから〝演出〟が誰によって考えられ実行されたのか確認できず、謎のままです。
鈴村と私との再会は、20年後の、兄義澄が急逝した1992年12月19日でした。
ひと月前に急性白血病と診断された義澄は、「おふくろを頼む」を遺言に、あれよあれよという間に病気を悪化させ他界してしまいました。
妻子ではなく母親を心配して人生を閉じた義澄。それはもしかしたら敗戦直後の10か月間に及ぶ極寒の北朝鮮の逃避行(一緒に逃げた軍官舎の仲間の3割から4割が落命)で、生まれたばかりの自分を守り抜いてくれた母親との誰も入り込むことができない〝絆〟がそう言わせたのかもしれません。
遺体が病院から実家に戻ると、さすがです。最初に家に来たのは鈴村でした。来たというよりも乗り込んできたという表現が合っているかもしれません。
「くにおみ、いいか、これは義澄の葬式じゃない。おふくろの葬式だと思え。明日の新聞に記事が載るようにしたから人がたくさん来る。大変なことになるぞ。手伝いを何人も送り込んでやるからそのつもりで頑張って仕切れ」
そう言って玄関を去る鈴村に深々と頭を下げていた千代子は、振り向きざまに私に言いました。
「分かったわね。それじゃあ、よろしく」
「ちょっと待ってくれよ。それじゃあ兄貴がかわいそうだろう。兄貴にふさわしい送り方をしてやろうよ」
と抗議をしましたが、母は聞く耳持たず。また兄嫁も夫婦関係に亀裂が入った状態でしたからどうでもよい表情を見せていました。
鈴村は自分の所に出入りする記者たちを手なずけていたのでしょうか、翌朝新聞各紙には兄の訃報が記事になって掲載され、実家の電話が鳴りっぱなしになりました。実は、千代子はその10数年前、岡崎市を含む西三河で初めての公立学校の女性校長になり、退職後は「婦人会館」の館長を務め、各地で講演を行う「女性のフロントランナー」として注目される存在だったのです。だから、新聞記事では、その長男が急逝したという書き方をされていました。でも、兄は会社勤めをやめて補習塾を自宅で開いていた〝名もない〟平凡な一市民です。新聞にその死去を報じられるような立場ではありません。
それを読んだ私は、「こんなクソ記事書きやがって」と兄の死を紙面に取り上げた記者たちをなじり、恨みました。
昼を過ぎると、鈴村と共に学校の校長・教頭クラスの教員たちが実家に現れ、千代子と打ち合わせをして慌ただしく通夜の準備をしていきました。くそまじめで地味に生きてきた義澄には似つかわしくない派手な通夜になりそうな気配です。私は母を人目のつかないところに呼び出しました。
「いい加減にしなさいよ。兄貴がかわいそうじゃないか。やつは名もない平凡な市民だよ。あなたの見栄でこんなにして」
「仕方がないの。鈴村先生のお考えがあるんだから。この場は私の顔を立てて」
珍しく懇願の表情を見せる千代子に〝母親の顔〟を見た私は、それ以上強くは言えずに、
「それじゃあ、せめて焼き場(火葬場)では僕と甥っ子たちの思ったような形で兄貴を送らせてもらうからね」
とだけ言ってその場を離れました。
高校生と小学生の甥には、
「焼き場では兄貴の好きだった歌で送ってやろう。やつが好きだった歌を10曲位選んでテープに録音しておいてくれるかな?」
と頼み、通夜と葬儀は〝鈴村応援団〟の邪魔にならないように全体のまとめ役に徹すると心に決めました。
案の定と言うか、予想をはるかに上回る弔問客が静かな住宅街に押し寄せました。返礼品が足らなくなり、3回追加注文するほどでした。通夜を行った部屋は、自宅を改造した塾の教室ですから一般的な家よりもかなりたくさん人が入れましたが、それでもとても全員は入りきれません。人の流れを作って順々にお帰り頂きました。
式を始める直前に雨が降り出しました。外に並んで待つ方たちに挨拶をしていると、「大変。葬儀屋さんが怒ってる」とお呼びがかかりました。
家の中に戻ると、叔父の一人が台所で「葬儀屋だったら天気予報を見てテント位用意しとけ!」と怒鳴り散らし、葬儀屋もそれを受けて「テントの注文は受けていない。そんな無理を言うんだったら引き揚げさせてもらう」とやり合っているではありませんか。「こんな時に問題を起こさんでくれよ」と思いながらふたりを引き離し、葬儀屋の言い分を聞き、説得にかかります。
「雨が降るなんて天気予報はなかったですよ。それをいきなり頭ごなしに怒鳴りつけられて……」
と興奮して訴える葬儀屋の社長は好人物で話の分かる人でした。こちらの話をよく聞いてくれ、機嫌がなおり事なきを得ました。こういった時には人間性が出るものです。言葉を荒らげていたのは高校の教員をする真面目一徹の叔父でした。他にも親戚の何人かが何かと口をはさんで私を困らせました。その点鈴村応援団は手助けすることはあっても、余計なことを言ったりしません。とても助かりました。
この一件を見ても分かるように、鈴村正弘という人物は、確かに一方的なやり方で物事を進めますが、状況を読む力、先見性、それに責任の取り方、いずれをとっても凡人ではありませんでした。それに比べ、一部の親戚は状況も分からずに口出しをしてくるだけです。その違いは明らかでした。
通夜に来てくれた弔問客の中に本多康希(こうすけ)さん、「隣の康ちゃん」がいました(本多家の人々について書いた第9回、第10回に登場)。30年ぶりの再会です。静岡の病院の勤務医になっていた康ちゃんは、仕事を終えた足で駆けつけてくれたのです。人込みの中に姿を見つけて近寄ろうとする私を康ちゃんは手で制し、義澄と最後のお別れをした後少し言葉を交わすとそのまま去りました。目が合った時、その目にはうっすらと涙が浮んでいました。心を揺さぶられた私は「こうちゃん、ありがとう」と、その背中に心の中でお礼を言いました。
義澄の教え子たちも来てくれました。
受験対策を主軸にして生徒を増やそうと言う兄嫁には耳を貸さず、義澄は頑固に「補習」にこだわりました。だから、生徒の中には当時問題視されていた〝茶髪の子〟もいました。そういった子たちが、おそらくみんなで話し合ったのでしょう。全員が500円玉を握りしめて、私の前に差し出してきたのです。私がその行為に胸が詰まったのは言うまでもありません。
翌朝の荒井山九品院で行われた葬儀にも多くの参列者がありました。
応援団を引き連れて鈴村が現れた時には、参列者の人波からどよめきが上がりました。元教育長というだけなのにまるで芸能人のお出ましです。しかし自分の存在はわきまえている方です。この場では出しゃばることなく、多くの事は語らずに葬儀が終わると静かに会場を後にしました(〝鈴村伝説〟では「どの様な場面でも傍若無人にふるまい、喋りまくってその場を去る」となっています)。
葬儀や火葬を巡ってもいろいろな出来事がありましたが、その辺りは「壮年期」編で詳しく書くことにして、ここではこれ以上触れないでおきます。
全てを終えて実家に戻ると、千代子が「明日鈴村先生の所へお礼に行くから同行しなさい」といつものように命令口調で言いましたが、私は「もう勘弁してくれよ。東京でやらなきゃいけない仕事が溜まっているからこのまま帰るわ」と断り、帰途につきました。
葬儀を終えて、私はひとり静かにあの世に行った義澄と〝話したかった〟のです。鈴村との付き合いに疲れ切った私は、鈴村を前にして大人しく頭を下げ続ける自信がありませんでした。また、千代子に鈴村とじっくり話す機会を持たせたいという〝親孝行〟な気持ちも、その一方で心の隅にありました。
こうして振り返ってみても、千代子(浅井家)にとって鈴村の存在の大きさは尋常ではありませんでした。10代後半で教生(教育実習)に行った先で訓導(指導)を受け、以来60年近く目をかけてもらった千代子が人もうらやむ教員人生を歩めたのも鈴村無くしては考えられません。
兄の死から8年後、巨星はこの世から姿を消しました。享年83歳でした。
千代子が、『櫻大樹―鈴村正弘先生追慕―』(2001年刊行)に寄せた追悼文にこんな記述がみられます。
「お世話になった長男が、平成四年に白血病で他界しました。逆縁ほど辛いことはありません。悲嘆のどん底だった時、先生は私の親しい人達に周りから支えてやるようにと、陰にまわって心遣いをしてくださいました。何かにつけて本当に長い間お世話様になりました」
そして詠んだのが、
『大往生の訣(わか)れといえど夜長星』
さらに、
「訃報が届いてすぐお宅に伺った時、先生の御遺体はまだ病院から戻っていらっしゃいませんでした。ふと庭を見ると、紅馬酔木(べにあせび)の花が真っ盛りで、その向こうの縁側の靴脱ぎ石の上に、昨日まで履いておいでだったであろう庭草履が、揃えられてありました」
と書き、
『どこからか声聞こえそう紅馬酔木』
と詠んで追悼文をしめています。
鈴村が亡くなった時、千代子はおそらく私の鈴村に対する見方を誤解したのでしょう。私のもとには訃報が届けられませんでした。知らせを受けていれば当然葬儀に参列、お顔を拝見してお別れをさせていただきました。
これ一つをとっても分かるように、この時点に至っても母子の心のボタンは掛け違ったままだったのです。
【これで「三河管理教育」の項はひとまず終わり、次回はまた「少年くにおみ」に戻ります】
(←第24回) (第26回→)